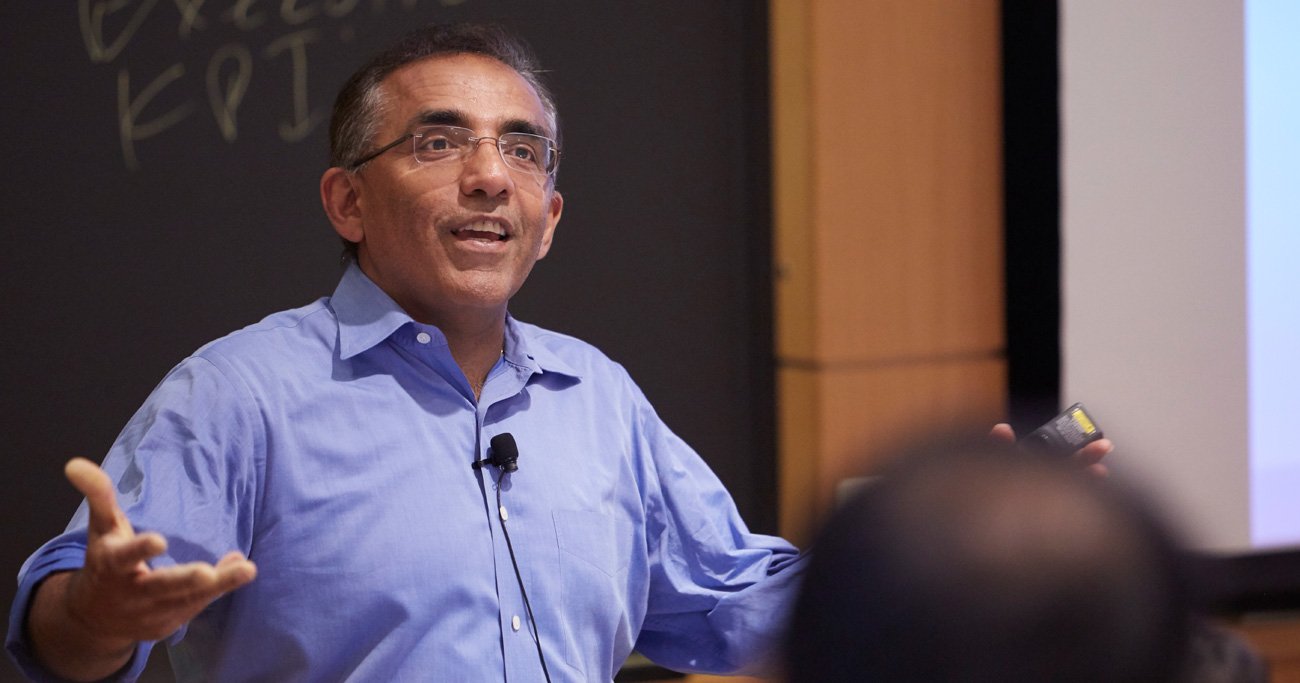慶應SFC環境情報2023年英語:解答解説と英文要約 / スタサプ、スタバ、イケてる会社にある魂
慶應義塾大学環境情報学部の2023年入試の英語について、全ての解答を紹介しています。
各段落の要約やプチ解説も入れておりますので、参考までにどうぞ。
環境情報2023の合格最低点
2023年の環境情報学部の合格最低点は246点。
得点率にすると61.5%でした。

大問1:3Dプリンターがもたらす新たな思考

- 題名:3-D Printers Give Us a New Way to Think
- 著者:クライブ・トンプソン / Clive Thompson (2015)
- 文字数:550字程度
【問題文冒頭】
Doctor Edward Smith some fiendishly difficult surgeries. A pediatric neurosurgeon at Boston Children’s Hospital, he often removes tumors and blood vessels that have grown in gnarled, tangled shapes. “It’s really complicated, defusing-a-bomb-type surgery,” he says.
大問1:筆者の主張
クライブ・トンプソン氏の主張をやや乱暴にまとめると、
Dプリンターをモノづくりの道具だけではなく、思考の補助ツールとして活用しよう。
ということになります。
大問1:各バラグラフ要約
各パラグラフをざっくりまとめると、以下の通りです。
- 小児神経外科医のスミス医師は、難しい外科手術の練習ため、3Dプリンターを活用している。
- 3Dプリンターを視覚化ツールとして活用することによって、スミス氏の手術時間は平均12%短縮された。このことは、3Dプリンターの使い方に新たな視座を与えてくれる。
- つまり、3Dプリンターを単にものを作るツールとして捉えるのではなく、思考ツールと役立てる。並べたり、考えたり、人に見せたりして、認知の補助をするツールとして活用する。
- 医師はこれまでMRIやCTスキャンを使い腫瘍を視覚化してきたが、スミス医師のように3Dプリンターを使えば、スクリーン上では不可能な空間的認知が得られ、対象をより深く理解することができる。
- 3Dプリンターが紙と同じように思考のツールとして普及するためには、リサイクル可能で分解性のある材料の誕生など、技術の向上が必要である。
- 3Dデータには、楽しくて興味深い活用がいろいろ考えられる。ものづくりの道具としてだけではなく、思考の道具として上手に使っていこう。
大問1解答(確定)
| 問題 | 解答 |
|---|---|
| 31 | 1 |
| 32 | 2 |
| 33 | 2 |
| 34 | 3 |
| 35 | 1 |
| 36 | 3 |
| 37 | 3 |
| 38 | 3 |
| 39 | 1 |
| 40 | 2 |
| 問題 | 解答 |
|---|---|
| 41 | 3 |
| 42 | 2 |
| 43 | 2 |
| 44 | 2 |
| 45 | 2 |
大問2:ロビンフッドは本当に正しい?

- 題名:Rethinking Robin Hood
- 著者:アンガス・ディートン / ANGUS DEATON (2016)
- 文字数:700字程度
ノーベル経済学者のアンガス・ディートン氏の文章から出題。
【問題文冒頭】
International development aid is based on the Robin Hood principle: take from the rich and give to the poor. National development agencies, multilateral organizations, and NGOs currently transfer more than $135 billion a year from rich countries to poor countries with this idea in mind.
大問2:筆者の主張
アンガス・ディート氏の主張を大まかにまとめると、以下の通り。
グローバル化は、労働力の安い場所に工場や仕事を移動させ、先進国の低所得層に被害を与えてきた。これは倫理的に受け入れられる代償であると考えられてきたが、その状況を放置すると格差がより拡大され、国が分断されてしまう。嫌かもしれないけど、自分達のためにも同国(アメリカ)の低所得層を救済しよう。
経済政策の基本は「どこかからお金を持ってきて、足りてない所に配る」であるが、自国の低所得者にも支援しようね、的なお話でした。
大問2:各バラグラフ要約
各パラグラフをざっくりまとめると、以下の通りです。
- 国際開発援助は、「金持ちから奪って貧しい者に与える」というロビン・フッドの原則(コスモポリラン優先主義)に基づいている。より少ない者はより多い者より優先されるという倫理的なルールで、さまざまな援助の根幹にある。
- 確かに、貧しい国の人々は、より差し迫った必要を抱えているので、コスモポリタン優先主義は表面上理にかなっている。
- 世界経済の成長とグローバリゼーションは、世界の貧しい国の人々を救ったが、豊かな国の人々にとっては害となった。しかも、損失被るのはより裕福で健康な国の人々だったため、倫理的に受け入れられてしまった。
- 経済のグローバル化を評価しているのはその受益者たちで、割りを食わされている先進国の低所得層にとって、グローバル化は素晴らしいものではない。
- 数百万人のアメリカ人が1日2ドル以下の生活をしており、これはインドやアフリカの貧困と同基準である。さらに、この収入で米国内に住居を見つけるのは困難なため、より深刻といえる。
- グローバル化によって、工場を失った町はや年は、財源を失い、教育の質を維持することさえ難しくなっている。これによって機会の平等も失われつつある。
- 市民として、互いに扶助しあう権利と義務があるが、国際的に考えすぎると、同国の貧困層を助けるという視点が抜けてしまう。
- 海の向こうの人ばかり支援して、線路の先の同国民を救わない放置していると、国が分断してしまう。そうならないように、同国の低所得の声にも耳を傾けよう。
大問2:解答(確定)
| 問題 | 解答 |
|---|---|
| 46 | 2 |
| 47 | 1 |
| 48 | 2 |
| 49 | 2 |
| 50 | 3 |
| 51 | 3 |
| 52 | 3 |
| 53 | 2 |
| 54 | 1 |
| 55 | 3 |
| 問題 | 解答 |
|---|---|
| 56 | 3 |
| 57 | 3 |
| 58 | 1 |
| 59 | 3 |
| 60 | 1 |
大問3:偉大な企業は創業の魂を守り抜く

- 題名:The Soul of a Start-Up
- 著者:ランジェイ・グラティ / Ranjay Gulati (2019)
- 語数:1350字程度
ハーバード大学経営大学院 ランジェイ・グラティ教授が書いた文章から出題。
いわゆる"イケてる"企業に共通してある、創業時の想いや魂の話。
【問題文冒頭】
There’s an essential, intangible something in start-ups—an energy, a soul. Company founders sense its presence. So do early employees and customers. It inspires people to contribute their talent, money, and enthusiasm and fosters a sense of deep connection and mutual purpose. As long as this spirit persists, engagement is high and start-ups remain agile and innovative, spurring growth. But when it vanishes, ventures can falter, and everyone perceives the loss—something special is gone.
ほぼ同内容の日本語版が2020年に電子書籍でも出ており、さらに発展的にまとめた書籍「DEEP PURPOSE 傑出する企業、その心と魂」が環境情報入試日の前日に発売されました。
大問3の内容をざっくり知りたい場合は、週間ダイヤモンドオンラインの連載記事がありますので、そちらをご参照下さい。
大問3:各バラグラフ要約
各パラグラフをざっくりまとめると、以下の通りです。
- スタートアップ企業には魂のようなものがあり、それが存在し続ける限り、成長していくことができる。
- 多くのスタートアップ企業が拡大と共に創業時の魂を失ってしまい、取り戻そうと苦慮している。
- 一部の企業は創業精神を忘れずに成長し続けている。ビジネスの成長には仕組みやシステムだけではなく、創業精神の維持も重要である。
- (*多くのベンチャーキャピタルやプライベート・エクイティ・ファンドが創業精神を幻想だと思っているのとは対照的に)多くの創業者は、使命やビジネスモデル以上の目的があると信じていた。
- 調査した結果、ユニークで刺激的な仕事環境を生み出すには「事業目的」「顧客とのつながり」「従業員の経験」の3要素が重要であることが分かった。
- 私が研究したすべてのベンチャー企業は、独自の活力ある「事業目的」を掲げていたが、それは会社の存在意義のようなもので、従業員は金銭以上の高い目標を持っていた。
- スタディサプリは「より多くの人に教材を提供することで、日本の教育格差を是正する」という考えのもと生まれた。それは、「社会に新しい価値を創造する」というリクルートのミッションと合致するものだった。
- スタディサプリは当初の精神を忘れず進化し続け、リクルートの教育事業の中心になった。
- 創業精神が消えたり、無くなったことに気が付くには、危機的な出来事が必要。FacebookやUberは、企業精神より利益を優先したことで公に謝罪したことがある。
- 創業精神の存在が深刻な場合、創業者はその取り戻すために戻ってくることがある。スターバックのハワードシェルツは、CEOに復帰して指揮を取り会社の魂を呼び戻そうとした。
- 会社の魂を守ることは内部統制や株式分割と並べて重要事項であるにもかかわらず、あまり重視されていない。「事業目的」「顧客とのつながり」「従業員の経験」の三位一体の精神を保つことができれば、企業は成長し続け、大きな存在になる。
*4段落:何と比較して"対照的"なのか分かりにくかったため、出題文ではなく原文から引用して補完しました。
大問3解答(確定)
| 問題 | 解答 |
|---|---|
| 61 | 1 |
| 62 | 2 |
| 63 | 3 |
| 64 | 3 |
| 65 | 1 |
| 66 | 3 |
| 67 | 2 |
| 68 | 2 |
| 69 | 1 |
| 70 | 2 |
| 問題 | 解答 |
|---|---|
| 71 | 1 |
| 72 | 2 |
| 73 | 2 |
| 74 | 1 |
| 75 | 3 |
| 76 | 3 |
| 77 | 3 |
| 78 | 1 |
| 79 | 1 |
| 80 | 2 |
| 問題 | 解答 |
|---|---|
| 81 | 4 |
| 82 | 4 |
| 83 | 2 |
| 84 | 4 |
| 85 | 2 |
| 86 | 1 |
| 87 | 4 |
| 88 | 3 |
| 89 | 3 |
| 90 | 1 |
\ お知らせ /
この記事を書いた慶應専門塾GOKOでは、一緒に慶應義塾大学を目指す生徒を募集をしています。
完全マンツーマンで密度の濃い授業を、オンラインで全国の受験生へお届けしております。
慶應を目指す受験生(とその保護者の方)は、以下よりお問い合わせください。
投稿者

- GOKOでは慶應義塾大学に進学したい受験生のために、役立つ情報の発信をおこなっています。こんな記事が読みたいなど、希望がありましたらお問合せページよりご連絡ください。