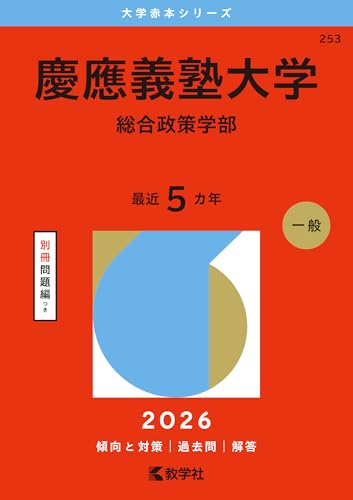慶應総合政策2022年英語:分析と出典一覧 / 10000年を超える時計
本記事では、慶應義塾大学 総合政策学部(SFC)2022年度英語について、
過去問の分析と、実際に使用された英文の出典元を紹介します。
Web上で公開されている記事については、リンク先から全文を読むことが可能です。
Webで公開されている記事はリンクから飛べば中身を読むことができます。
記事の性質上、解答のヒントや解答そのものの言及もあります。過去問を解く前に余計な情報を入れたくない人は十分注意してください。
この記事を読むメリット
- 総合政策学部の英文のレベルや分量がわかる
- 自分の英語力を確認することができる
- 入試英文を実際の生きた英文の形で読める
それでは早速いってみましょう!
2022英語の難易度と英文量
出題形式や構成は例年通り。
2022年度の各大問の英文量は以下の通り。
- 大問1:556語
- 大問2:773語
- 大問3:1,208語
合計:2,537語
前年と比べると分量的にも難易度的にも易化しました。
大問1:人類の起源を揺るがすモロッコの化石
- 原題:Moroccan fossils shake up understanding of human origins
- 著者:ウィルダナム / Will Dunham
- 英文量:556語
- 難易度:やや易
ロイター通信の2017年の記事が元ネタ。以下のリンクより全文読むことができます。
大前提として覚えておいてほしいのが、
- これを書いている私も、読んでいるあなたも「ホモ・サピエンス」である。
- かつて人類は複数種いたが、現在残っている人類はホモ・サピエンスだけ。
- ホモ・サピエンスの歴史はざっくり20~30万年前(諸説あり)
私たちは普段、「人間」と「動物」を対立的に考えがちですが、生物学的には人間も動物の一種です。
人間=ホモ・サピエンス。
ときどきでいいので、思い出してみてください。
大問2:1万年使えるものを作るには?
- 原題:How to Build Something That Lasts 10,000 Years
- 著者:アレクサンダー・ローズ / Alexander Rose
- 英文量:773語
- 難易度:標準
イギリスのNHKことBBC(British Broadcasting Corporation)の2019年の記事が元ネタです。
この記事では、ロング・ナウ財団(The Long Now Foundation)で「1万年時計」の建設に取り組むアレクサンダー・ローズ氏が、
- 歴史的事例
- 現代の長期プロジェクト
- 物質科学・工学・思想
といった観点から、極めて長期間持続するものを設計するための教訓をまとめています。
物語は、著者が日本・伊勢で宮中行事を目にした体験から始まります。
日本に古くから受け継がれてきた伝統・建築・組織を通じて、「長く使い続けられるものとは何か」を考察していきます。
1万年計画
アレクサンダー・ローズ氏は、もともとロボット兵器や軍事技術の分野に関わっていた人物ですが、現在は「1万年時計(The 10,000 Year Clock)」という壮大なプロジェクトに携わっています。
日本ではほとんど知られていませんが、Amazon創業者ジェフ・ベゾスが出資していることでも有名です。
このプロジェクトを進めている非営利団体The Long Now Foundation、この組織の幹部が今回の著者アレクサンダー・ローズ氏です。
計画の概要を約5分でまとめた動画もあります。
非常に分かりやすいので、ぜひ一度ご覧ください。
ご本人のTwitterをみたところ、こんな写真が紹介されていました。

いろんなものづくりに関わってるみたいですね。
大問3:ソフトパワーの無価値さ
- 原題:The Irrelevance of Soft Power
- 著者:イランマナーとガイJゴラン / Ilan Manor & Guy J. Golan
- 英文量:1,208語
- 難易度:やや難
国際関係や国際政治をメインに扱う学術系メディア「E-International Relations」 に、2020年に掲載された記事が出典です。
著者2名はいずれも大学所属の研究者です。
全文がPDFで公開されており、以下よりダウンロードできるようにしました。
大問3:内容解説
本論文は、ソフトパワーが無意味になりつつある理由は、その理論的欠陥ではなく、国際環境の変化にあると主張しています。
特に、中国・インド・アメリカという三大国間の競争の激化が、ソフトパワーの有効性を大きく低下させていると論じています。
これらの大国が国際政治の舞台で支配的な役割を果たすようになった結果、中小国は、価値観の共有ではなく、短期的な戦略的利益に基づいて大国と駆け引きを行わざるを得なくなっている、というのが論文の中心的な主張です。
ソフトパワーの定義と従来の役割
論文はまず、ジョセフ・ナイによって提唱されたソフトパワー(Soft Power) の概念を確認します。
ソフトパワーとは、軍事力や経済力といったハードパワーとは異なり、文化・価値観・政治体制などを通じて、他国に影響を与える能力を指します。
冷戦期のように、価値観の対立が明確だった時代においては、ソフトパワーは自国の魅力を示し、国際的な支持を拡大するための重要な手段として機能していました。
現代の国際政治における変化
論文は、21世紀の国際政治を中国・インド・アメリカの三大国が競合する時代と位置づけています。
これらの国々は、経済力・軍事力・技術力のあらゆる面で他国を圧倒しており、中小国が単独で対等に渡り合うことは、ますます困難になっています。
戦略的同盟の重要性:
このような状況下で中小国が取る戦略が、短期的な戦略的同盟の形成です。
中小国は、
- 大国と共同で交渉する
- 大国同士を競わせる
といった形で生存戦略を立てるようになります。
これらの同盟は、長期的な価値観の共有ではなく、
短期的・実利的な利益に基づいて形成されるため、非常に柔軟です。
たとえば、
ある目的のためにはA国と、
別の目的のためにはB国と同盟を結ぶ、
といったことが可能になります。
ソフトパワーの相対的な地位の低下
このような国際環境では、ソフトパワーは相対的に重要性を失います。
なぜなら、各国が重視するのは価値観の共有ではなく、自国の短期的利益にどれだけ貢献できるかだからです。
文化や価値観を通じた「魅力の発信」は、大国との交渉において、決定的な武器とはなりにくくなります。
その代わりに各国が重視するのは、戦略的同盟における「望ましいメンバー」としての地位です。
この「望ましさ」は、
- 経済の安定性
- 技術インフラ
- 地理的条件
など、複数の現実的要素によって評価されます。
多極化の時代から三大国の時代へ
論文は、現代を
- 単一覇権国(アメリカ)の時代
- 二極構造(アメリカ vs ソ連)の時代
の延長線上ではなく、三大国が中心となる新たな時代として捉えています。
この時代においては、「パワーの機能の仕方そのものが変化しており、ソフトパワーの役割は限定的にならざるを得ない」というのが論文の結論です。
まとめ
本論文は、現代の国際政治においては「文化や価値観による魅力(ソフトパワー)よりも、短期的な戦略的利益に基づく現実的な駆け引きが中心になっている」と主張しています。
ロシアによるウクライナ侵攻を目の当たりにしている現在、この記事のタイトルと内容は、改めて強く実感させられるものがあります。
今回紹介した英文は、下記の過去問にも掲載されています。
しっかり過去問対策をして、慶應入試に挑みましょう!
投稿者

- GOKOでは慶應義塾大学に進学したい受験生のために、役立つ情報の発信をおこなっています。こんな記事が読みたいなど、希望がありましたらお問合せページよりご連絡ください。